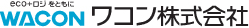2018年の食品衛生法の改正の一部として、2020年6月に施行されたHACCPですが、1年間の移行期間を経て、いよいよ2021年6月1日から「原則義務化」となります。今回は「聞いたことあるけれどよくわかっていないな」という方に、HACCPをできるだけ「わかりやすく簡単」に解説したいと思います。
HACCPとは?
ずばり、「食品業界における衛生管理の手法」です。
Hazard(危害), Analysis(分析), Critical(重要), Control(管理), Point(点)の5つの言葉の頭文字を並べて作られた造語で、読み方は「ハサップ」または「ハセップ」で、どちらでもOKです。
つまり、「原材料を仕入れてから食品を製造・出荷する全ての工程の中で、衛生管理上どのようなリスク(Hazard)があるのかきちんと調べて(Analysis)、そのリスクを最小限に抑えるために重要(Critical)な工程(Point)をきちんと管理(Control)しましょう。」ということですね。

この手法は、世界保健機関(WHO)と国連食糧農業機関(FAO)の合同機関である食品規格 (コーデックス) 委員会から発表され、各国にその採用が推奨されてきました。
ちなみにHACCPは、1960年代の月を目指す「アポロ計画」において、絶対に食中毒を起こしてはならない宇宙食の高度な衛生管理方法としてNASAが考案したのが始まりらしいです。
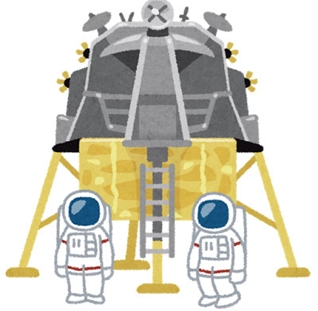
HACCP義務化の対象者は?
原則は全ての食品等事業者が対象です。(食品製造業や食品販売業、飲食店など、食品の製造や加工、販売などを行う事業者)
しかし、事業形態や規模によって①「HACCPに基づく衛生管理」が必要な場合と、②「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を行う場合の2パターンに分かれます。
①「HACCPに基づく衛生管理」の場合
そのままですが、HACCPに沿った衛生管理に取り組むことが求められます。
②「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の場合
小規模な営業者等(個人経営のカフェや米屋、従業員数が50人未満の事業所など)が対象で、各業界団体が作成する手引書を参考に、簡略化されたアプローチによる衛生管理を行う。
具体的に何するの?
HACCPの 7原則12手順
HACCPには「7原則12手順」と呼ばれるガイドラインがあり、食品衛生のレベルを守るために、これらの手順に沿いながら製造を行っていきます。

手順の1~5番は衛生管理上のリスクを分析するための準備にあたり、6~12番で実際にリスクを分析し、HACCPプランを具体的に作成していきます。
おわりに
2021年6月1日からの義務化に向けて、食品事業者様はすでに実施の準備を行っておられるはずです。
さらりと書きましたが、調べれば調べるほど、HACCPを導入し、運用していくことが簡単なことではないことがわかりました。
「食品を安心安全に提供したい」という、食品事業者様の思いがあってこそ導入できるものなのだと思います。私たちの食生活を支えてくださっている食品事業者様に感謝です。